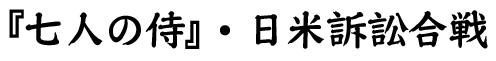MGMと東宝に対する訴訟は1992年8月7日に東京地裁に提起された。前に述べたJSBの件で訴訟を起こした時に、多数の新聞社から電話があり、夜中まで説明をさせられた事があったので、今度はプレスリリースを用意して待っていた。しかし、思った程電話の問合せが無く、拍子抜けした。翌日の毎日新聞の朝刊には次のような記事が載った。
|
「七人の侍」再映画化権巡り
黒沢監督、米社を逆提訴
|
黒沢監督の名画「七人の侍」(1954年公開)の再映画化をめぐり、黒沢監督と黒沢プロなどが「再映画化の権利は黒沢監督側にある」として、米国の大手映画配給会社メトロ・ゴールドウィン・メイヤー(MGM)を相手に権利不存在の確認を求めて7日、東京地裁に提訴した。MGMが再映画化権は自社にあると主張、米裁判所に訴えたのに対抗した措置。 訴状などによると、「七人の侍」を配給した日本の東宝は58年、米映画会社アルシオナ・プロダクションに原作シナリオの再映画化権を譲渡、米国版「七人の侍」の「荒野の七人」が製作された(60年公開)。黒沢監督らはこのアルシオナへの権利譲渡が著作者の許可なく行われたと、73年に東宝を相手に東京地裁へ提訴。78年の地裁判決は「脚本の著作権者が映画化権を持つ」と黒沢監督側に軍配を上げ、再映画化権譲渡は「無断譲渡」の形になった。
ところが昨年12月、MGMがアルシオナから再映画化権を承継したとして東宝、黒沢監督らを相手に権利確認などを求めてカリフォルニア州地裁に訴えた。
黒沢監督側の乗杉純弁護士は「MGMは『七人の侍』をテレビ映画化する意向のようだ。米国での訴訟では遠隔地ということもあって十分な防御ができないため提訴した」と話している。
訴訟を起こすことに決めてから実際に提起するまでに4ヶ月近い時間がかかってしまったが、このような訴訟は初めてであったので、いろいろな問題を解決しなければならなかった。日本の裁判所は日本語しか受付けないので、証拠書類を含めて45頁もあるMGMの訴状を和訳するのに随分と時間がかかった。法律問題としては、MGMに対する訴訟について、日本の裁判所が管轄を認めてくれるのか、また認めさせるにはどのような議論をすべきかについて判例・学説を検討した。ひとつ残った問題は訴状の送達で、東京地裁が国際条約に定めた手続に従ってMGMに訴状を送達するのに3ヶ月以上の期間を必要とした。この期間を短縮する方法は無かったので、仕方なく、東京地裁に対して速やかに送達してくれるようにとの上申書を提出した。同時に、MGMに対する訴訟と東宝に対する訴訟を併合審理(同じ法廷で裁くこと)してほしいとの希望を述べたが、これは受け入れられず、MGMに対する訴訟は第37部が、東宝に対する訴訟は第35部が裁くことになった。
黒澤明ら3人の脚本家がMGMに対して訴訟を起こしたことは、グローバート弁護士を通じてMGMに伝えられていたが、訴訟提起から1ヶ月程してMGMの日本における代理人と称する弁護士から電話があった。その弁護士は、私のミシガン大学ロースクールの先輩で、ミシガン大学の日本における同窓会の理事として時々顔を合わせていた山川洋一郎氏であった。山川氏は、MGMが訴状の送達に拘わらず、日本における訴訟につき応訴すると述べた。これで大きな問題のひとつは解決し、実質的な戦いが始まった。
2つの訴訟は1ヶ月強の間隔で期日が入り進行していった。MGMに対する訴訟においては、MGM側は予想通り管轄を争ってきた。東宝に対する訴訟においては、詐欺が成立するか否かが争点となった。後者は、これまでの裁判例を見ても先例として参考になるようなものは無く、裁判所も困惑しているようであった。黒澤側が詐欺を立証するために使える材料はMGMの訴状に添付されていた手紙の写しと1990年の和解契約書のみであった。これらの手紙が存在することを隠しながら和解契約を締結した東宝の行為が詐欺と言える程度に悪質であることを裁判所に印象づける必要があった。しかし、材料がこれだけに限られていると、様々な表現を使うように工夫をしてみても、同じ主張の繰り返しになってしまう。
米国の訴訟においては、証拠開示手続が続いており、ダンボール箱が一杯になるほどの書類が送られて来ていた。米国訴訟においては、MGMが東宝と黒澤側を訴え、東宝が更に黒澤プロダクションを訴えていた。東宝の黒澤プロダクションに対する訴訟は、東宝がMGMとの訴訟に負けた場合に、MGMから請求される損害賠償額を事前に黒澤プロダクションに求償するという内容の訴訟であった。証拠開示手続もこのような関係で行われていたので、米国から送られてきた資料の中には東宝が提出したものもあった。証拠開示手続の中で相手方に書類の提出を要求するためには、書類を具体的に特定する必要はない。例えば、「1978年の七人の侍事件東京地裁判決に関する全ての書類」としてもいい。このような要求に応じて東宝が提出してきたと思われる書類のコピーが1992年12月にアメリカから送られてきた束の中にあった。そこに謎を解く鍵があった。
その書類とは、1978年の東京地裁判決の訴状、再度申入書及び調停申立書であったが、訴状の中の「訴えの原因」第3項及び第4項が30年前の出来事を簡潔に述べているのでそれを次に引用する。
|
「3、昭和35年(1960年)11月頃東宝より、原告等3名に対し、「七人の侍」のシナリオの映画化権を、米国のアルシオナ・プロダクション・インコーポレーテッド(以下アルシオナと略称する)に譲渡することに承諾してほしいとの要請あり、3名は、これを承諾した。(この譲渡は出版権の設定と同じく3年で消滅する旧著28条ノ4、かつ、慣習による1本の映画化権を意味する)其後原告等は東宝がアルシオナより如何なる条件にて譲渡契約を成立させるのか、またその条件等についても改めて相談があるものと期待していた。然るに其後原告等3名は、東宝より5000ドルと2000ドルを受取つたのみで、契約の内容は全く知らされなかった。此金員は米国映画と日本映画の製作規模の大きさからいって明らかに少額に過ぎるので不審に思っていたところへ、1本限りの映画化権譲渡の筈にもかかわらず、「荒野の七人」に続いて「続荒野の七人」の映画化決定が新聞のニュースで報知されたので、原告等3名は驚愕して東宝に対し、何時の時点に於て、如何なる条件を以つて契約をなしたのか厳重に抗議し、その契約内容の公開を迫ったが、東宝は言を左右にしてそれを明らかにせず、昭和43年(1968年)に至り原告等3名の調査に依つてやつと次の如き事実が判明した。
4、即ち、東宝は、前記承諾書ができた昭和35年(1960年)より、既に2年以前の昭和33年(1958年)9月に、原告等に一切内容を知らせることなく、アルシオナと契約し、前記の5000ドルと2000ドルもこの契約に依るものであることが判明したが、この契約で東宝は、アルシオナに対し、シナリオの権利に関しては東宝が全世界を通じて唯一の著作権々利者であると僭称し、これを永久に売却処分している事実が判明した。」
|
この訴状は、その当時黒澤明ら脚本家3名を代理していた勝本弁護士が作成したもので、再度申入書及び調停申立書から見るとこの訴訟の3年ほど前から勝本弁護士が脚本家3名を代理して東宝と交渉していたようである。これらの書面の内容から、概ね次のような事実が推測出来る。
1958年9月、東宝はアルシオナに対して「七人の侍」の再映画化権を与える契約を締結したが、東宝はそれが脚本家の許諾を得ていないため無断譲渡になることにはまだ気付いていなかったものと思われる。「七人の侍」のリメイクである「荒野の七人」は1960年に製作され、同じ1960年の11月に東宝は黒澤明ら脚本家3名から前述の承諾書を取付けている。この時脚本家達が、「荒野の七人」が製作されたこと、またそれが「七人の侍」のリメイクであることを知っていたか否かは明らかではないが、東宝がアルシオナとの契約を既に締結していることについては知らされていなかった。既にその契約が締結されていることを前提に話しが進められていたとすれば、アルシオナとの契約を日付をもって特定し、脚本家達が何に対して同意したかが明白にできた筈である。その後脚本家達は東宝から5千ドルと2千ドルを受領したが、アルシオナとの契約の内容については知らされなかった。
1966年に、アルシオナから権利を譲り受けたミリッシュ・プロダクションズが「荒野の七人」の続編である「リターン・オブ・ザ・セブン」という劇場用映画を製作した。これを知った脚本家達は、承諾書によるリメイクの許諾は1本に限定したものであると考えていたので、東宝に抗議し、契約内容を開示するよう要求したが東宝はそれに応じなかった。1968年頃脚本家達は独自の調査で東宝とアルシオナの間の契約の内容を知り、東宝に協議を申し入れた。「再度申入書」によれば、この最初の申し入れは1968年2月10日付の書面をもってなされたが、それに対し東宝は2月17日付の書面により、「本問題の所管提案者である川喜多、藤本両重役が現在渡米中なるをもってお申越の2月20日までに回答できない、従って両重役の帰国後緊急に回答する」と述べた。しかし、その後東宝が話合いに応じようとしないので、脚本家達は1970年10月1日付で解決案を提案した。これに対しても東宝から色よい返事が無かったため、1971年6月23日に再度申入書として新たなる解決提案をした。
結局話合いによる解決は出来ず、1971年8月19日に脚本家達は東京簡易裁判所に調停の申立てをした。この調停によっても解決は出来ず、1973年5月に脚本家達は東京地方裁判所に訴えを提起した。
以上のストーリーは、脚本家達の代理人である勝本弁護士の作成した書面に基づくものであって、一方的な主張であると言われるかもしれない。しかし、このストーリーは1978年の東京地裁判決の内容と照らし合わせてみると、概ね正しいのではないかと思われる。私は、第5章「保険会社の疑問」で、東京地裁判決の理由中に承諾書の性格に言及した部分があると述べた。脚本家達は、上述のように承諾書は脚本の映画化権をアルシオナに譲渡することに関するものである、と述べている。これに反し東宝は、背景、登場人物の名前、性格付け等において、脚本の内容に変更を加えることにつき承諾を求めた、と述べている。承諾書の文言は、第7章「承諾書出現」で引用した通り、東宝の述べるような著作者人格権に関するものではなく、脚本の映画化権の譲渡を承諾するものであることを明記している。「承諾」が1回のみ存在したことについては、脚本家も東宝も争っていないため、今回の訴訟で東宝が証拠として提出してきた承諾書が1978年の東京地裁判決で問題とされている承諾書であることには間違いがない。1978年の判決で原被告が対立する主張をし、裁判所がそれに対して何ら判断していないという事は、その訴訟において承諾書が証拠として提出されなかったことを意味している。承諾書の文言は脚本家達の主張する内容に沿っているため、脚本家達がその時に承諾書を持っていたならば当然証拠として提出したであろう。脚本家達はもともと承諾書の写しを持っていなかったのか、又はそれを紛失してしまったのか、今となっては真相は明らかにすべくもない。東宝はと言えば、今回の訴訟で承諾書を提出してきた以上、前回の訴訟の時にも持っていたのであろう。前回の訴訟の時には紛失していて、今回の訴訟になって倉庫の奥から発見された、というような話は現実的ではない。
では、何故東宝は承諾書を隠して、承諾が著作者人格権に関するものである等という嘘の主張をしたのだろうか。それは、承諾書を出してしまえば、それが脚本家達の主張を裏付けることになり、訴訟に負けることになると考えていたからであろう。この推論が正しいとすれば、東宝は、承諾書が不完全なものであり、東宝がアルシオナに与えた権利を追認する効果を持たないという認識を有していたことになる。どのように不完全であったかについては、いろいろな可能性があるが、少なくとも東宝がアルシオナとの契約の内容を脚本家達に説明してその内容全体についての承諾を求めたことはなかったであろう。本来であれば、アルシオナとの契約書及びその日本語訳を添付しその内容全体について承諾するという契約書を脚本家達と作るべきであった。それが出来なかったということは、東宝の対応に後ろめたいものがあったことを示唆している。例えば、「荒野の七人」の製作について知った脚本家達が抗議をしてきたので、東宝はその1本についてのみのリメイクを認める契約をこれから締結するので承諾して欲しい、と言ったのかもしれない。