「この文章の英文も作らなくてはいけないんですけど、和文はこれでよろしいでしょうか?」と宮下が聞いた。
「木で鼻をくくったような文章ですね」と君原が言った。
「こういう場合、日本の会社だったら、世間を騒がして申し訳ないとか、こういう事態になったことは遺憾であるとか、何か言うんじゃないですか。主要な新聞の今日の夕刊をだいたい見ましたが、全部1面に載っていますから、この事件を無視するのは通らないと思うのですが」
「でも、うちは事務所としては何も悪いことはしていないんだよ。あれをやったのは黒田さん個人なんだから」と寺本は言った。
「しかし、黒田先生は、創立パートナーで代表パートナーなんですから、その人の行為について事務所が全く言及しないのもおかしいんじゃないですか?」
「それは違うね」と寺本は君原を睨みつけながら言った。
「会社の代表取締役が何かをやったのと今回は全く違うのだ。会社の代表取締役は、会社の機関なんだから、たとえ、やったことが個人的な悪事だったとしても、会社自体が謝るというのは分かる。
法律事務所はこれとは違う。法律事務所には法人格は認められていないし、税務申告をするのも弁護士が各々やるわけだ。法人化が許されないという制約を受けている法律事務所が、不祥事の時だけ、法人のような顔をして謝らなければいけないのは、それ自体不公平じゃないか」
そんな理屈が世間で通ると思うのか、と君原は思ったが、こんなことで議論をするのがばかばかしくなって、黙った。
宮下が次の議題に移ろうとした時に、山崎がおずおずと手を挙げた。
「この文面には、黒田先生が辞められたということが、何も触れられていませんが、これでいいのでしょうか?つまり、黒田先生は、創立パートナーで、これまで寺本先生と一緒に事務所を支えてこられた方ですので、そういう方が辞められる場合には、何か一言あってもいいのではないでしょうか」
「黒田先生が辞めたことに言及するとまずいことになるんですよ。事務所を辞めただけでは済まないでしょう。何故辞めたか、弁護士登録を抹消したからだ、何故抹消したのか、犯罪を犯したからだ、とこのように続くでしょう。そこまでいくと、事務所としても関係がないでは済まなくなって、謝罪めいたことを言わなければならなくなる。さっきも言ったように、私は、事務所は何も悪くはないと思う。だから、事務所は謝るべきではないし、謝らなければならないような立場に事務所を追い込むべきではない」と寺本は言った。
山崎は、威圧的な口調で話す寺本を不満そうな顔をして見ていたが、何も反論しなかった。
「では、次の議題……サイモン・ヘイスティング&ゴールドマン……ゴールドマンでしたっけ……からのお話に移りたいと思います。
私はこれ、とてもいいお話だと思うのですけど……何か問題があるのかしら。すぐお金がいただけるというのがとても有り難いと思うのですけど」と宮下が言った。
「金が入ってくるなどということは、どうでもいいことだけど、私はこれを一つのチャンスだと見ているのですよ。これで、われわれは本当にインターナショナルな仕事ができるようになる。これが実現すれば、私はSH&Gのワールドワイドのオペレーションも見ていかなければならなくなる。1年の半分くらいはニューヨークのヘッドクオーターで仕事をしてくれと言われているんですが、それもやむを得ないかなと思っている。50を過ぎてこういうことを始めるのは正直なところしんどいんですけれど、一つのチャレンジだと思って、皆さんのために頑張りたいと思います」。有無を言わせないという強い調子で寺本が言った。
T&Kの入っているビルから100メートルほど離れたところにある喫茶店で、この会話をイヤホンで聴いていた川上は思わず笑ってしまった。パートナーズミーティングが行われている会議室の、電話が載っているサイドテーブルの下の段には、ステープラーやセロハンテープなどを入れた箱が置いてあり、その中には電池を取り替えたばかりの、SH&Gの名前の入った電卓も入っていた。
「買収の話は、われわれの自治権が確保されればそれほど問題はないように思うんですが」とシニアパートナーの田中が言った。
田中は、これまで、黒田の証券関係の仕事で生計を立てていたのだが、黒田がいなくなった今、寺本の力を借りて、証券関係のクライアントが落ちていくのを防ぎたいと思っていた。
「その点は私も一番気にかけているところで、皆さんが肩身の狭い思いをすることがないことは保証します。私は、日本よりもアメリカで名前が通っている人間だから、彼らは私の意見を無視はできないはずです。私がSH&Gのパートナーになれば、皆さんがこれまで以上にいい環境で仕事ができるように、体を張って頑張るつもりです」と寺本が答えた。
「寺本先生がこれだけ言ってくださっているんだから、私は、何も心配することはないと思いますが」と宮下が言った。
「私は今週の金曜日からニューヨークに行って、具体的な条件について話を詰めてこようと思っています。もちろん、皆さんの承諾なしには、何も合意するつもりはありませんが、私が交渉することについて異議のある人はいますか?」
「お願いします」と元気よく田中が言い、何人かが頷いた。君原は不愉快そうに横を向いていた。
次の朝、珍しく、山崎が君原の部屋に来た。山崎は、部屋に入るとドアを閉めた。パートナーの部屋のドアは、開けておくのが普通だったから、これは内密の話があるというしるしだった。
「君原先生。昨日のこと、どう思いますか?」
山崎が辛うじて聞き取れるほどの小さな声で聞いた。
「昨日のことって?」
「あの挨拶状のことですけど、あれではまるでわれわれが黒田先生を切り捨てた、と言われても仕方がないように思います。暴力団だってもっと情があると思います」
「寺本と黒田の関係というのはよく分からないんだな。表面は仲がよさそうにしているけれど、内心では相手が滅びればいいと思っているようなところがあるんだよね」
「考え過ぎかもしれませんが、今回の事件には腑に落ちないところがあるんです。問題のインサイダー取引は、この間のTOBの時のものですよね。そうだとすれば、株の売買から逮捕まで1ヶ月ちょっとしかないわけで、あまりにも早すぎます。96年の例の事件の時には、特捜は1年以上かけて捜査をしていました。今回は、よほど確実な証拠が手に入ったとしか思えません」
「内部告発、というようなこと?」
「ええ。ひょっとしたら……寺本先生が……」
「それはないでしょう。ライバルを蹴落として事務所が自分1人のものになったとしても、その事務所自体が潰れてしまったらしょうがないでしょう」
「普通はそう考えるわけですが、今回は、例の買収の話がありますからね……」
「買収に反対していた黒田先生を消すということか……」
「それが1つですし、もう1つは、われわれに対しても、黒田先生のいない事務所は生き延びていくことはできない、だから買収に応じるしかない、というプレッシャーをかけるということです」
「随分危ないゲームだなぁ。うまくいかなければ、事務所を潰すという結果だけが残るかもしれないわけでしょう」
「全くの推測ですけれど……寺本先生に、よほどいいポジションが提供されるとか、買収の金額とは別な裏金が出るとか……考えればいろいろあります。とにかく、昨日の寺本先生の態度は、これで買収に進めるという安堵のようなものばかりが目立って、黒田先生が逮捕されたことについての悲しみのようなものは、全く見られませんでした」
「それで、山崎先生はどうするの?」
「あの会議の前までは、黒田先生からいただいたクライアントをしっかりと守って、この事務所でやっていこうと思っていたのですが、何か嫌になりました。このまま行けば、買収ということになるんでしょうが、そうなれば、事務所は変わってしまうと思います。黒田先生のような人情味のあるというか、大雑把というか、ああいうやり方が通用しなくなり、コストパフォーマンスのみを考えた仕事のやり方になっていくんでしょう。そんなことなら、この機会に事務所を出ようかと、考えているところなんです」
「なるほどね。僕も、あの会議が始まった時は、買収に反対して、リストラや何かで事務所を建て直すということを考えていたのだけど、そんなことで寺本先生と対立してゴタゴタやっていたら、本当に事務所が潰れてしまうと思った。だから、言いたいことはたくさんあったんだけど、敢えて何も言わなかった。ということは、あの雰囲気からすると、買収に賛成していることになってしまうのだよね」
「もう元には戻れないとは思いますよ」
「どこから狂ってきてしまったのかなぁ。頭脳の割に体が大きくなりすぎた恐竜みたいなものかなぁ。しばらく前から、環境の変化にうまく対応できなくなっていたと思うのだ。今回の事件にしても、われわれはどう対処していいか分からなくて、おろおろしているだけだ」
「私は今まで、黒田先生に従って、自分の意見も主張しないでここまで来たわけですけど。君原先生がそういう私の生き方に対して、批判的なのは十分承知していますが、今が、そういうものから抜け出られるチャンスだと思えるのです。これを逃せば、また、長い物には巻かれろ、的な人生を送っていきそうな気がするんです」
「弁護士が組織の中で生きていくっていうのは難しいもんだよね。僕も、この事務所では、弁護士が5、6人の時から、組織作りでいろいろと努力してきたつもりだけど、やればやるほど生きにくい社会ができてしまったという気がするね。だから、少人数で、気ままにやっていくのも魅力は感じるね」
一瞬の沈黙のあと、山崎は、意を決したように言った。
「端的に言いますと、先生が、私と、パートナーシップを組むことは考えられますか?」
「面白い話だなぁ。今まで考えたことはなかったけれど……」と君原は言って、あとに続く言葉を探した。
君原は、山崎とは一定の距離をおいてつきあっていたので、彼とのパートナーシップがどのようなものになるかはすぐには想像ができなかった。山崎には黒田から引き継いだ優良なクライアントがたくさんいたから、新事務所の財政的な基盤を考えた場合には、いい相手かもしれなかった。その反面、現在のところ君原よりも収入が多い若い弁護士と組むのは、いろいろとやりにくいところもあった。君原は回答を引き延ばすことにした。
「パートナーシップを組んで1つの事務所でやっていくのも一つの方法だけど、もう少し距離をおいて、提携というような形でやっていく方法もあるんだよ。僕は、コンピューターを使って弁護士業務をどのように改善できるか、ということを研究する会に入っているんだけれど、そこで、1つのアイディアを発表しようと思っている。15日の夜その会合があるんだけど、一緒に出ない?」
「是非お願いします」
川上は、さっきから、FMラジオをいろいろな角度に向けて音声を捉えようとしていたが、ほとんど成功しなかった。
川上は、山崎が君原の部屋に入っていきドアを閉めた時に、これは重要な会議に違いない、と直感した。すぐ自分の机に戻り、受信を試みたが、発信器である電卓に入っている電池がかなり消耗していること、君原が、たぶん電卓を机の引き出しの中に入れていること、山崎の声が普段でも聞こえないほど小さいことが相乗的に作用して、意味のある会話はほとんど捉えられなかった。
東京地方裁判所に起こされた、ハーキュリーズピクチャーズを被告とする訴訟の第1回口頭弁論は、6月14日の午前10時に予定されていた。法廷は6階の611号法廷で、希花は10分前に法廷に着いた。法廷の前の事件表を見ると、10時の弁論は5件指定されていた。傍聴席には既に弁護士が2人、記録を読みながら待っていたが、希花の事件の相手方の弁護士はまだ来ていなかった。被告側から既に答弁書が提出されており、そこには予想されたとおり、管轄を争う旨の主張が述べられていた。
今日は訴状と答弁書の陳述で終わるはずだった。いつも希花より先に法廷に来ている伊藤が今日は遅かった。君原は渉外事務所のパートナーの多くがそうであるように、法廷には滅多に出てこなかった。もっとも訴訟の経験の乏しい君原が出て来てもあまり役には立たなかったが。
数分後に、相手方の下田という若い弁護士が到着し、今日提出予定の準備書面です、と言って準備書面の副本を希花に渡した。準備書面は10頁余りのものであり、仮に管轄の主張が認められなかったとしても、という書き出しでハーキュリーズピクチャーズがリメイク権を有していると主張しているようだった。準備書面と一緒に、書証(証拠として裁判所に提出される書面)も何枚か出されており、その中に「覚書」というものがあった。乙第六号証とされたその覚書を読んで希花は愕然とした。
そこにはこう書かれていた。
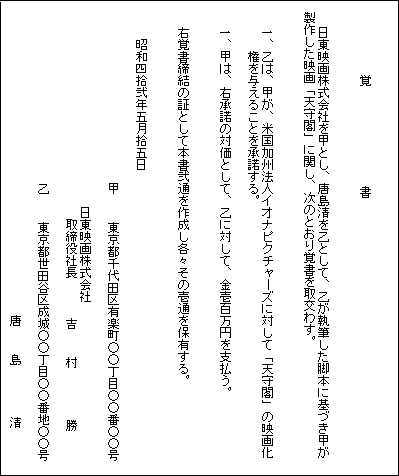
希花は、一瞬、頭の中が真っ白になり、何も考えられなくなっていた。後ろから声がした。
「滝川先生、遅くなってごめんなさい。事務所で、宮下先生に捕まってしまって、出るのが遅くなって……」
伊藤が、珍しく慌てたようで、額の汗を拭いながら立っていた。
「伊藤先生。こんなのが出てきたわ。どうしたらいいの」
伊藤は一読して呟いた。
「これが本物だったら、この訴訟はわれわれの負けですね」
10時に3人の裁判官が入廷し、希花達の事件が最初に審理された。訴状、答弁書の陳述と、審理は段取りを追って進んでいったが、希花は上の空だった。
裁判長が書証について被告代理人と話をしていた。被告代理人の下田弁護士は、クリアフォルダーに入っていた書類を取り出し、廷吏に渡した。廷吏はこれを裁判長に渡した。裁判所が原本の確認を済ませたあと、廷吏は書証の原本を希花に渡した。希花は他の書証には見向きもせずに、乙第六号証の覚書を穴のあくほど見つめていた。
それはB5判の用紙にタイプで打たれており、用紙は30年の歳月を感じさせるように黄ばんでいた。印影は薄くなっていたが、鮮明であった。奇妙なところは、その文書の本文が書かれているすぐ上の余白が大きくえぐり取られていることだった。まるで、鋭い歯をもった動物が噛みきっていったかのように楕円形に切りとられていた。希花は、伊藤と、首をかしげながら、その部分を斜めから見たり透かしてみたりしたが、何も分からなかった。
「被告代理人にお尋ねしたいのですが」と立ち上がって希花が言った。
「この乙第六号証の上の部分ですが、切りとられた跡がありますが、これはどうしたんでしょうか?」
「それは、私が日東映画株式会社から受領した時からそのような状態でした。不審な点がおありでしたら、そちらにも原本が一部あるはずですから、お確かめになったらいかがでしょうか」
「唐島プロダクションに原本があれば苦労はしないわよ」
重い足どりで裁判所からの帰り道を伊藤と歩きながら、希花が言った。
「唐島プロダクションには何もないという話だったですよね」
「あのハンコが本物だったら、唐島監督がリメイク権を与えたということを、追認したことになってしまうわ。あれをひっくり返す方法はないのかしら」
「仮にこちらに原本がなくても、唐島プロダクションの側で誰が交渉したかが分かれば、その人を証人に呼んでくることはできますよね」
希花と伊藤は事務所に着くと、すぐ君原の部屋に行き、今日の裁判所での顛末を説明した。
君原は被告の提出した乙第六号証のスタンプが押された覚書の写しをじっと見ていた。
「これをひっくり返さないと、われわれは負けだな」
「でも、原本が破かれていたっていうのは絶対おかしいですよ。切り口も新しいようだったし、何か都合の悪いことが書かれていたから破いたに違いないわ」と希花が言った。
「とにかく、唐島監督にすぐ連絡をして、こちらサイドの原本を見つけよう。何れにしても打ち合わせる必要があるから、なるべく早く会議を入れよう」
君原は唐島監督の訴訟のことも気にはなったが、ここ数日間は自分のことで頭がいっぱいだった。山崎から、一緒に独立をしないか、という誘いを受けるまでは、君原は自分が独立することは想像もしていなかった。君原は、T&Kが設立されて3年ほど経ったときに、寺本に誘われて、パートナーになる直前であった前の事務所を辞めてT&Kに移ってきた。それから15年が経ち、君原が入った時は5人しかいなかった弁護士が、今や70人近くになっている。その中で、黒田が辞めたために、君原はナンバー3で、実質的には寺本に次ぐ地位にあった。本来であれば、何十人かの弁護士を引き連れて出るのならともかく、1人で飛び出すことは考えられないことだった。
しかし、客観的な情勢を見ると、このまま事務所に残っているのが得であるかは、はなはだ疑問であった。黒田が辞めたことにより、T&Kの財政事情は逼迫しており、倒産も考えられないことはなかった。大法律事務所が倒産した例はなかったので、どのような事態になるかは予想がつかなかった。会社が倒産した場合には、破産法とか会社更生法などによって処理の方法が示されているが、法律事務所は法人ではないから、そのような手続きは適用にならない。結局、全パートナーが連帯して責任を負うことになるのだが、その責任の負い方について取決めがないので、混乱は避けられない。さらに、財政的に破綻しようとも、各弁護士は依頼者に対して事件を処理するという責任が残っているので、それは事務所の清算と同時に進めなければならない。それを怠れば、依頼者からは損害賠償を請求されるだろうし、弁護士資格を剥奪されることにもなりかねない。
寺本は、このような最悪の事態を避けるために、米国の法律事務所にT&Kを売るべきだと言っている。黒田が辞めた今となっては、この話は救済策の色彩を帯びて、パートナーの中にもこれに同調する者が増えつつある。しかし、この話は、黒田が逮捕される前からあったもので、それに黒田は反対していたのだ。だから、山崎のように、寺本が黒田をはめた、と考える者も出て来る。
君原にとって腑に落ちないのは、そもそも何故寺本がこの買収話に飛びついたのか、ということだった。あの頃は、T&Kの危機説を主張していたのは君原のみであって、寺本はそれに興味を示していたとは思えなかった。そのような危機意識なくして、日本一になったばかりの大事務所のトップのパートナーが、何故身売りを考えたのだろうか。君原は、何かこの話には胡散臭いところがあると思っていた。買収の相手方とは、寺本のみが接触しているので、買収の条件として何が話し合われているかは他の人間には分からない。結果的に、寺本のみがいい思いをして、他のパートナーは裏切られることになるのかもしれない。何れにしても、買収されてしまえば、人事権はアメリカの事務所が持つわけだから、予め保証を与えられていないパートナーは、不安な思いをすることになる。
買収が終わってから、その後の状況を見極めて、それから辞める辞めないを考えてもいいのではないか、と一度は君原も考えた。しかし、買収が終わってから辞めることは、裸一貫で出るということである。つまり、法律事務所の財産はクライアントだから、アメリカの法律事務所は、T&Kのクライアントの持ち出しを認めるわけがない。買収に応じてお金をもらうことは、各パートナーが自分のクライアントを売り渡すということだ。君原は、今更ゼロからクライアントを開拓することは、とても考えられなかったので、買収後に辞めることは弁護士を廃業するに等しかった。
考えられる可能性を全て分析した結果、君原は独立を決意した。独立するについても、いくつかの可能性があり、1人で飛び出すというものから、事務所のパートナー、アソシエイト、スタッフのかなりの部分を連れて出るという形までいろいろな段階が考えられた。過去の渉外事務所の分裂の例では、ナンバー2の弁護士が、トップの弁護士だけをおいて残りの全員を連れて出てしまった、という極端な例もあったが、ナンバー1とナンバー2が別れる場合にはそれぞれが持っているクライアントの数に応じて事務所が割れるのが普通だった。君原は、寺本に対抗できるほどの力はなかったから、事務所を割って出るにしても、他の力のあるパートナーと語らって、新たに共同事務所を作るというのが唯一の可能性だった。この場合には、突出した力のある者がいなければ、さらに分裂が起きる可能性があった。君原は、しばらく前から、法律事務所が規模を売り物にすることに懐疑的になっていたので、小規模な共同事務所を作ってそれをまた日本一にしよう、という気はさらさらなかった。君原が考えていたのは、小規模な事務所のネットワーク化で、まだ誰も成し遂げたことのないものであった。
「う〜ん」と唐島監督はうなった。
唐島監督は、乙六号証の覚書を見て、一生懸命何かを思い出そうとしていた。
「見たことがあるような気もするんだが……それとも、別な会社の話だったかなぁ。とにかく僕は、こういうものには興味がなくて、言われるままに判を押していたのだよ」
「ここに押してあるハンコは監督のものですか?」と君原が聞いた。
「これは覚えているね。10年ぐらい前まではこのハンコを使っていたよ」
「この当時、つまり、1967年の頃ですけれども、唐島プロダクションで契約の話をしていたのは誰ですか?」
「山本だったっけねぇ?」と唐島監督は田代の方を見て聞いた。
「私は、その頃まだ生まれていなかったので、知らないんですけれど、その頃唐島プロダクションにいた人に聞きますと、そうらしいですよ」
「その山本っていう人は、今どこで何をしているんですか?」と君原が聞いた。
「ちゃんと調べてあります」と田代が得意そうに言った。
「山本六郎という人で、監督が中国で撮った『揚子江』のプロデューサーをしていた人です。唐島監督の下を去ってから、ピンク映画の製作をしばらくしていたようですけれど、今は映画界を全く離れているようです」
「何をしているの?」と唐島監督が聞いた。
「風俗営業のお店を5、6軒持っていて、羽振りがいいそうです」
「今どこに住んでいるか分かりますか?」と君原が聞いた。
「いえ。でも、今興信所に頼んで調べてもらっていますので、あと2、3日で分かると思います」
「覚書の原本を持っているとしたらこの人ですね」
「住所が分かったら、私が行って話をしてみましょうか?」と田代が言った。
「そうですね、田代さんには行っていただきたいが、1人では危ないから、滝川が一緒に行くようにしましょう。女性が行けば相手も気を許すだろうし、私が行くよりいいでしょう」
希花が内線電話をとると君原からで、新宿にタイ料理を食べに行こう、と誘われた。希花は仕事が忙しかったので最初は断ったが、君原が、どうしても話したいことがあると言うので行くことにした。
靖国通りから区役所通りへ入ってすぐのところにあるその店は、タイの王宮料理を食べさせることで人気があった。希花達が着いた時には、店内はほぼ満席で、タイ料理独特の香りで部屋中が満たされていた。君原が予約していた席は窓際で、それはそれでよかったのだが、隣りに20人程の団体がテーブルをつなげて座っていて騒がしいことこの上なかった。君原は生春巻き、海老の春雨スパイシーサラダ、トムヤムクンとチキンとバジルの葉の唐辛子炒めを頼み、赤ワインをオーダーした。君原はいつになく疲れた様子だった。
「今日話したかったのはね……僕がT&Kを辞めることを伝えたかったのだ」
「え!辞めるって、独立するっていうこと?」
「そう」
「誰と一緒に出るの?1人じゃないでしょ」
「山崎さんから、一緒に出ないかって誘われたんだけれど、あの人とはちょっと波長が合わないからなぁ。お互いに協力していくということにはなったけど」
「山崎先生はちょっとくたびれるわよね。それで、誰と組むの?」
「君だよ」
「えっ!私なんかクライアントもいないし、足手まといなだけよ。それともアソシエイトとしてこき使おうっていうの?」
「君と一緒に仕事ができたらいいなと思っただけだよ」
「寝たから?そういうことで、何か責任を感じてくれていると言うんだったら、それは心配ないのよ。私は自立しているから」と希花は微笑んだ。
「いや。ただ一緒にいられればいいなと思っただけで……」
「でも、私にも将来があるし。先生が本当に独立して大丈夫か、分からないでしょ」
「いや、そのことだったら心配はいらないよ。ユナイテッドモーターズとは話をして、僕についてきてくれることになったし、他に、日本の一部上場の企業も3社ばかりある」
「でも、寄らば大樹の陰、ということもあるしなぁ」
「大樹といったって、T&Kはもうすぐ買収されちゃうんだよ。そうすれば、アソシエイトなんかいつ首を切られるか分からない」
「外資だからってそんなひどいことはしないでしょ」
「いやぁ、僕は前に、準会員系の事務所にいたからよく分かるけど、まともな人間には耐えられないよ」
「ふぅん」
「僕の前いた事務所は、ラッセルというアメリカの弁護士が作った事務所だった。彼は、極東裁判で日本人の大物を弁護したということで一目置かれていた人物だったけれど、日本のことは、死ぬまで植民地としか思っていなかったようだ。彼が30年間日本にいて覚えた日本語は、『右』『左』と『止まれ』で、これはタクシーに道を指示する時に必要だから覚えたそうだ。
事務所の中でオフィシャルに使われるのはもちろん英語だけだし、パートナー会議も全部英語でやっていたらしい。彼に評価されるのは、英語のできる奴だけで、弁護士としての能力は関係ない。彼に気に入られていたのが、マイク木村、これはれっきとした日本人の弁護士だ。でも、自分のファーストネームである誠という名前は誰にも呼ばせず、どこにいってもマイク木村で通していた。ラッセルはその木村を通して入って来る情報ですべてを判断していたから、ラッセルがボケてきた最後の2、3年は、木村が絶大な権力を持っていた。木村の機嫌を損ねれば、パートナーでも首を切られるという話だった」
「それからもう20年近く経っているのだから、だいぶ違ってきているのではないかしら。日本もその頃に比べれば、大国になってきたのだから」
「いや、アメリカ人のやり方っていうのは変わらないと思うよ。パックス・アメリカーナで、どこに行っても、自分だけが正義だと思っている。買収されてしまえば、われわれはみんな雇われ弁護士になるわけだし、いつ首を切られたって文句は言えない。純粋な労働者だったら、労働基準法で守られるけれど、弁護士の場合は、委任関係だから、それもおぼつかない」
「寺本先生は、ニューヨークのパートナーになるのかしら?」
「さぁ、あれだけ一生懸命になっているからには、当然何かいい話があるんだろう。ニューヨークのパートナーになるのは当然のこととして、他にも裏金があるとか、いろいろあるかもしれない」
食事が終わったら、君原は、またあの派手なネオンサインのついたホテルに私を誘うのだろうか、と希花は考えた。どうしても嫌だというわけではなかったが、積極的にそうしたいという気持はなかった。いつもは手入れのいい君原の髪が、今日は伸びすぎていて鬱陶しかった。忙しくて、しばらく床屋に行っていないのかもしれない。横から君原の髪を観察していた希花は、もみ上げのところが真っ白になっているのに気がついた。よく観察してみると、長い髪も、根元のところが白くなっている。これは、ヘアダイかヘアマニキュアに違いない、と希花は思った。そう思ってみると、君原は決して若くはなかった。希花は、自分の隣で赤ワインをちびちび舐めるように飲んでいるこの中年男が、本当に自分が憧れていたあの君原なのか不安になり、確かめるように横顔を見た。
希花と田代は、唐島監督のショーファー(お抱え運転手)付の車で、元プロデューサー、山本六郎の帰りを待っていた。バブル期に建てられたと思われる豪華な作りのマンションの前は公園になっていて、公園の横に止めてある車からマンションへの人の出入りが明瞭に把握できた。
「田代さん。あの3階の窓に明かりが点けば帰ってきたということだから、ずっと見張っていることはないわよ」と、双眼鏡をマンションのエントランス方向に向けている田代に希花が言った。
「あの男かもしれない。今タクシーから降りてきた禿げた男」と田代が小声で言った。
2、3分して3階の明かりが点いたので、田代と希花は車を降りてエントランスへ向かった。
「滝川さん、ここはオートロックだ。どうしよう」と田代が大きなシャンデリアの下の部屋番号を書いたボードの前で立ち尽くしていた。
「ここで、唐島監督の代理人ですとか言ったら、入れてもらえないでしょ。誰かが出入りしたらそのスキに入り込もうか?」
「ちょっと私にやらしてくれる」と希花が言って、403とボードにあるボタンを押した。
「部屋番号が違うわよ?303よ」
「ちょっと黙っていて」
「誰ですか?」とスピーカーを通して声がした。
「洗濯屋です。いつもお世話になっています」と希花が言った。
ドアの方でカチッという音がして、ガラスのドアがスルスルと開いた。
「滝川さんて、頭がいいだけかと思ったら、結構ワルなのね」と田代が感心したように言った。
「ただのワルなのよ」
303号室のチャイムを鳴らすと、ドアが30センチほど開き、海坊主のような赤ら顔の男が顔を出した。唐島プロダクションにあった、30年前に撮られた写真に、唐島監督と一緒に写っていた男に間違いがなかった。
「何だ。お前等?」
「山本六郎さんですね」と田代が言った。
「そうだ。表札に書いてあるだろう」
「唐島清の姪の田代と申します」
山本は、唐島の名前が出た時に一瞬怯えたような表情を見せたが、唐島がどこにも隠れていないことを確認すると、ふてぶてしさを取り戻した。
「だからどうしたというんだ」
「ちょっと、お話ししたいことがあるのですが……」
「俺は忙しいんだ」
「大きなお金がからんだ話なんですよ」と希花が口を挟んだ。
「金がどうしたっていうんだ。ここで言ってみなよ」
山本の目が光った。
「長くなるのでここでは話せません」と希花が答えた。
「しょうがねえな。入れよ」
山本は、2人を招き入れると、ドアの鍵を閉め、チェーンをかけた。
2人は30畳程の広いリビングルームに通された。厚い絨毯が敷かれていて、羽根布団の上を歩いているようだった。部屋にはアジアの各地から集めてきたと思われる仏像や仏頭が飾られていて、アメリカ映画に出て来るオリエンタル趣味の富豪の部屋のようだった。
「何だ、その金の話っていうのは?」
2人をソファーに座らせると、山本は聞いた。
「山本さんは、前に唐島プロダクションの面倒を見てくださっていたと聞きましたので、もしやご存知かと思いまして。
監督の『天守閣』ですが……日東が製作したものです……あの映画のリメイクの契約を日東がアメリカの会社と結んだことをご存知でしょうか?」と田代が言った。
「それで?」
「その契約は、監督の知らないうちに結ばれたもので、無効なものなんです。そこで、多分、監督が文句を言ったんだと思うのですが、日東が、その契約について、監督の追認を取るための覚書を提案してきたようなのです」
「へぇ、びっくりしたね。昨日の今日でまたその話か」
「またって何ですか?」と希花が聞いた。
「その覚書っていうのが、欲しいんだろう」
「昨日、誰かが来たんですか?」
「500万円払うってさ。俺は、そんな安くはないよって追い返したんだ」
「誰です、それ」
「綺麗な姉ちゃんだよ。色の白い」
「色が白くって、切れ長の眼をした、博多人形みたいな人?」と希花が聞いた。
「知らねぇよ。関係ないだろ」
「滝川さん。どういうことなの?誰なのその人?」と、話についていけなくなった田代が希花に聞いた。
「いや、違うかもしれない……」希花は、独り言のように言った。
「それで、お嬢さん達は、いくら払うっていうんだい」
「でも、あれは監督のものなんですよ。あなたが持っているのがおかしいのよ」と田代が言った。
「誰も持っているなんて言っていないよ。嫌なら帰れよ。さあ、帰れよ」
「分かったわ。金は出せるわ。だから現物を見せて」と希花が言った。
「本当かね。見せてやってもいいが、おかしなことを言い出したら、いつでも燃やして灰にできるんだぞ」と山本はドスの利いた声で言った。
山本は隣の部屋に行き、茶封筒を持って戻ってきた。そして、封筒の中から、四つ折りになった黄ばんだ紙を取り出し、広げて田代に手渡した。
覚書と題された書面は、乙第六号証と全く同じように見えた。ただ、乙第六号証で切りとられていた部分に、手書きで書き込みがあった。覚書の第一項の2行目の「与えることを承諾する。」の上に「1本に限り」という言葉が手書きで加えられていてそこにハンコが2つ押してあった。この挿入された文字を加えて読むと、覚書の第一項は「乙は、甲が、米国加州法人イオナピクチャーズに対して『天守閣』の映画化権を1本に限り与えることを承諾する」となる。
1本に限って映画化権を与えるというのはどういうことなんだろう。希花は、この発見を喜んでいいのか、分からなかった。1本だけなら、イオナピクチャーズが『天守閣』をベースにした映画を作ってもいいわけだから、それが今回ハーキュリーズピクチャーズが作った映画ということになったら、それには唐島監督の承諾が与えられていることになってしまう。
「日東と、この件で話をしていたのは、山本さんですよね」と希花が聞いた。
「そうだ。俺しかいなかったからよ」
「この、1本に限り、というのは、どうして入れたのですか?」
「そりゃ、1本はできちまっていたからしょうがないが、それ以上のはダメだっていうことよ。ちゃんと、監督のことを考えて、俺が交渉して入れさせたんだ」
「1本できていたって、それ、何ですか?」
「何にも知らねえんだなぁ。『ウォーリアーズ・パス』っていうのは知らないか。知らねえよなぁ、全然当たらなかったからな」
「それが、1本に限り、の1本なの?じゃあ、1本はもうその時にできていたんだ……」と希花はホッとして言った。
「それがあったから、俺達が騒いだんだよ。映画ができなきゃ、日東が勝手なことをやったってことは、俺達には分からないんだよ」
「それで、1本だけはできてしまっているから仕方がないけど、それ以上作るには別な承諾が必要だということね」
「そうだよ。そうすれば、2本目から、また金が取れるだろ」
「よかったわ」
「なるほど……誰かが2本目を作りたがっているんだな。それとも、もうすでに作ってしまったのか」
「それで、いくらだったら譲ってくれるの?」
「いくら払えるんだ?」
希花と田代は顔を見合わせた。
「監督は、しばらく映画を撮っていないので、お金ないんです。家も借家だし……」と田代が哀れっぽく言った。
「お話にならねぇよな。もう帰んなよ。あっちにも渡さないからよ。どうせ、俺は金なんていらないんだ。500万なんて、3日もあれば入って来るよ。寝てても入って来るんだよ」
「じゃあ、何が欲しいんですか?」と希花が言った。
「そうだな……女は腐るほどいるし……。ところで、あんたは何者なんだ。監督の何なんだ?」
「私は、唐島監督の弁護士です」と希花が言った。
「へぇ……女弁護士か。女弁護士っていうのは、ブスばっかりかと思っていたよ」
「この人は、ただの弁護士じゃないんですよ。バイリンガルで、ニューヨークの弁護士資格も持っているんですよ」と田代が口を挟んだ。
山本の目の色が変わった。
「ほぅ。それでいて、体もいいじゃないか。俺は、脱がなくたって、いい体しているかどうか、すぐ分かるんだよ。目利きっていうのかな」と山本は好色な眼で希花を見ながら言った。
「それと交換っていうのはどうかしら?」と希花が言った。
「それって……何がいいたいんだ?」
「私が一晩つきあったら、あの紙をくれるっていうのはどう?」
「面白いじゃねえか。こんな女弁護士は、テレビには出てこないぞ。上等じゃないか。今晩か?」
「今日は、ちょっとダメなの。あれだから」
「あれか……」
山本は生唾を呑み込みながら言った。
「ダメよ、滝川さん。そんなことをしちゃいけないわ」と田代が希花の耳元で囁いた。
「じゃあ、来週だったらいいんだな」
山本は手帳を取り出してスケジュールを見ていた。
「来週の、金曜日は、7日だよな……7日か」と言って山本は少し考えた。
「こういうのはどうだ。7日の金曜日に、ここでちょっとしたパーティーがあるんだよ。超大物が来る仮面パーティーだ。いや、本当にお面をつけてもらうんだ。顔を見たら誰でも分かるような、お偉方が来るんだ」
「芸能人?」と希花が聞いた。
「とんでもない」馬鹿にしたように山本が言った。
「アッと驚くような大物代議士。次官クラスの官僚。それにオーナー社長。それもスター経営者だ」
「それと、私と、何の関係があるの?」
「女の子が足りないんだよ。各店のナンバー1を出して、人数は揃っているんだが、なんていうのかな……輝くような女がいないんだよなぁ。この女と寝たらあとはもういいっていうような、そんな子が欲しかったんだよ」
「私が、それだっていうの?」
「肩書きがすごいって言っているんじゃないぞ。そんなのは言わなくたっていい。そんなのは話していれば自然と分かる。あんたを初めて見たときから、俺も久しぶりにその気になっていたんだよ。そういうものを、あんたは持っているんだよ」
「嬉しいわ、そこまで言っていただけると」
「じゃあ、いいんだな。何人も相手をすることになるけど、いいんだな」
「SMはいやよ」
「それはない。部屋が汚れるからな」
田代は、このとんでもないやり取りに眼を白黒させていた。
希花が、急に立ち上がり、お腹が痛いのでトイレに行きたいと言った。何を思ってか、山本は、また卑猥な笑いを浮かべながら、希花をトイレに案内した。
トイレから戻ってきた希花は、もう一度覚書を広げて、しげしげと眺めた。そして、元のように四つ折りに畳むと、何を思ったのか、その紙片をブラジャーとふくよかな胸の間に押し込もうとした。
「何をしているんだ。それを返せ!」と山本は怒鳴った。
「冗談よ。どうせ、来週もらえるんだから」と希花は言った。
希花は紙片を茶封筒の中に戻し、テーブルの上に置いた。山本が、それを取り上げ、中を見ようとした。
「黒い下着を着けていっていいかしら?レースのスケスケのやつ」と希花が聞いた。
「いいんじゃないか。みんな喜ぶと思うぞ」と、卑猥な笑いを浮かべて山本は言った。
「じゃあ、私達もう帰るから」
唐突に希花は言って立ち上がった。ドアの方にさっさと歩いていく希花を、田代も追いかけた。
山本のマンションの部屋を出て、ドアが閉まるのを確認すると、希花は、田代に向かって早く、と言うと、エレベーターを使わずに階段を駆け下りた。田代は何が起きたのか分からずに、転びそうになりながら希花の後にしたがった。
唐島監督の車に乗り、山本のマンションが見えなくなったところで、初めて希花は口を開いた。
「ごめんなさいね。訳の分からないことをしてしまって」
「本当にそんなパーティーに行くの?そんなことまでしてもらうわけには行かないわ。 あの覚書は手に入らなくてもしょうがないわ。他の方法を探しましょう」
「もう、手に入ってしまったわ」と希花は言って、ブラジャーの中に手を入れると、黄ばんだ紙片を取り出し、それを広げた。それは、茶封筒に入れて、山本のところに置いてきたはずの覚書だった。
「どうしたの!」
田代は眼を見開いて叫んだ。
「ちょっと、手先が器用なだけなのよ」
「いつ……どこで?」
「私は、前に法廷で、日東の持っている覚書の原本を見たでしょ。だから、それがどんな大きさでどんな色をしてどんな紙質かっていうのは分かっていたの。そして、似たような紙を手に入れることができた。だけど、分からなかったのは、山本のところにあるその紙がどんなふうに折り畳まれているかということだったの」
「それで、そういうふうに折ったわけ?どこで?」
「トイレで」
「それで、あの時にすり替えたの?手品みたい」
「それはどうってことはなかったんだけれど、そのあとが危なかった。山本が、茶封筒を取って中を見ようとしたでしょ。あの紙を広げて見られたら、一巻の終わりだから、そこで注意を逸らそうとしたの。最後に言った言葉は、窮余の一策というやつ。田代さん、私が色情狂だと思ったでしょ」
「頭が混乱して分からないわ。全部嘘だったの?全部お芝居だったの?」
「さぁね。来週、パーティーに出るかもしれないわ。結構面白そうじゃない」
李華美はリビングルームのソファの上でまどろんでいた。
華美は、新宿駅の方向へ真っ直ぐに伸びている広い道路を歩いていた。道路の両側には、いずれ超高層ビルが建てられるはずの広い四角い土地が暗い穴のようにいくつも続いていた。黒い雲に覆われた空に向かって、高い煙突のようなビルが2本立っていた。高いビルの最上階には、綺麗なレストランがあるということだったが、華美は行ったことはなかった。レストランの明かりは、強い風に吹き流されてきた雲に遮られて、あとには、どこまでも続く闇が残った。厚い雲の中から突然UFOが降りてくるのではないかと、華美は空を見上げた。華美は、道路から、周りに背の高い草が生い茂る、四角い土地に降りていった。そこは、昼間はグラウンドとして草野球で賑わっていたが、今は誰もいない。
華美は、手に手に棒を持った上級生の男子生徒と、グラウンドの中央で向かい合っていた。「生意気だぞ、朝鮮人!」とその中の1人が言った。
いつの間にか華美は取り囲まれていて、敵は四方から迫っていた。華美は、身構えようとしたが、足が動かなかった。地面にはりついたように、足が上がらなかった。
太い腕が、華美の細い胴に回され、華美の体は宙に浮いた。ロバート・パク。あなたなのね。私が困った時にいつも助けに来てくれる。
華美の体は、夜空高く浮上し、超高層ビルを見おろした。
突然、花火のように、下界の明るさが増し、光の花園のようになった。超高層ビルが林立し、自動車の赤いテールランプが、どこまでも続いていた。
何故、ロバートとは最近会えなかったのだろう。華美は考えた。でも、何か恐いことに行き当たりそうだったので、考えるのを止めた。このままずっと飛んでいたかった。
下界が、急に騒がしくなった。繁華街の喧噪が押し寄せてきた。
隣の部屋で、リーリーッと呼び出し音がうるさい。テレビ電話だ。
モニターには「電話がかかっています。応答しますか?」という表示が出ていた。川上がYESをクリックすると、キングの不愉快そうな顔が大写しになった。
「さっき、寺本から電話があって、君原から辞表が出た、と言っていた。どういうことなんだ?」
「辞表が……そんな兆候はなかったわ。寺本もそんなことは言ってなかったし……」
「パートナーやアソシエイト6人だかの辞表が一度に出てきたそうだ。他の連中はどうでもいいが、君原は困る」
「私に文句を言われても困るわ。買収は請け負ったけれども、誰が残るかっていうのは条件じゃないでしょ」
「それは分かっているよ。でも、君原にあの訴訟を持って出られたら、何のために買収をしたか分からない。何か方法はないのか?」
「君原の弱みっていうのは、アソシエイトの滝川っていうのとできていることぐらいだわ」
「それじゃあなぁ……そういう材料を使って、反発されたら、もうおしまいだからな。もっと情報が欲しいんだ。使いものにならないような情報でも、分析していけば、いろんなことが分かってくる。もっとデータはないかな?」
「データ……ないことはないわ。役に立つか分からないけど」
「何だ、それは。どんなデータなんだ?」
「君原を辞めさせないというのは、私の請負の範囲には入っていないわよね」
「確かにそうだ。それはエキストラサービスということになる」
「そのエキストラサービスについては、エキストラフィーも出るの?もし、私の取ってくる情報で君原がT&Kに残ることになったら、いくらもらえるのかしら?」
「契約のやり方を間違えたかもしれないな」
「もう遅いわ」
「分かった。プラス10万を出そう」
「少ないわ」
「じゃあ、20万」
「30万」
「25万でどうだ?」
「いいわ」
「クリスティーヌ、君は大した奴だよ、弁護士になれば、きっと一流になるよ」
「本当にそうなるかもしれないわ」
「それはともかく、この25万というのは、成功報酬だよ。失敗したらゼロだ」
「失敗はしないつもりだけど、この前のようには簡単ではないと思うわ。100メガ以上あるファイルだから」
「100メガ?百科事典でも送ろうっていうのかい」
「データベースなのよ。T&Kが、パートナーが持っているフロッピーディスクの中に入っているすべての文書をコンピューターのハードディスクに入れて、それをデータベースにしようとしているの。君原の分はほとんど完成していて、彼のだけで15メガぐらいあると思う。君原の分だけを分離するのは難しいから、ファイル全体を送りたいの」
「なるほど……それだけ分量があれば何か見つけられるかもしれないな。インターネットで送ってくれるのか?」
「そうするつもりだけど、ファイルが大きいので、転送に時間がかかるけれど」
「なるべく早く欲しいんだよ。明日にでもできないかなぁ?マリックの言っていた3ヶ月の期限は、7月16日に切れるんだよ。もう2週間ぐらいしかない。その期限までにあの訴訟が、われわれの思い通りになるようになっていなければならないのだ」
「分かったわ。できるだけのことはする。それから、あの覚書とかいうのを手に入れる話だけど、山本は、500万ではイヤだと言っているんだけれど、どうしたらいいのかしら?」
「どうしても手に入れなければならないものではないから、もう少し様子を見るかな。とにかく、あれが、唐島監督のところにないことが分かっただけでも、大成功だ。連中も、あれを手に入れることはできないだろうから、われわれがこの前東京の訴訟で出した書証が唯一の証拠になるのだ」
「盗み出せっていわれればやるけど、本当にいいのね?」
「そこまでやらなくてもいいよ。それよりも君原の方が大切だ。そっちの方を全力でやって欲しい」
「いつものメールアドレスでいいのね、ファイルを送る先は」
「あれでいいよ。あのアドレスは闇のルートで買ったものだから、私までは辿れない」
「明日の晩メールを送るわ。100メガのファイルと請求書もね」
― 2000年 7月 ―
1
「どう、私ってちょっとすごいでしょ」
希花は伊藤の顔の前で覚書をヒラヒラさせて言った。
「要するに窃盗したということですね。刑法235条。10年以下の懲役」
「自力救済よ。唐島監督の所有物ですもの」
「この場合は仕方ないですかね。でも、善良なる市民にはなかなかできないことですね」
「私が犯罪者のような言い方ね」
「初めてじゃないでしょ」
「中学までは万引きをしていたけれど、最近は何もやっていないわ」
「……」
君原が昨日からバンコクに出張しているので、希花と伊藤は相談して、7月10日の次回期日前に裁判所に提出できるように書証を準備することにした。伊藤はすぐにそれにとりかかり、ついでにこの覚書がどのようにして作成され、どのような法的意味があるかについて述べた準備書面も作成した。伊藤が書き終えようとしていた時に、川上がクライアントからもらった菓子を配りに部屋に入ってきた。
「今、川上さんが部屋から出てきたけれど、どうしたの?」
会議から戻ってきた希花が言った。
「ただ、お菓子を配ってくれただけですよ」
「この覚書のことは、事務所の中でも秘密にしておいた方がいいわ。絶対に狙われているんだから」
「事務長に言って、金庫に入れてもらいましょうか?」
「ダメよ。あんな金庫、プロにとっては、鍵がないのも同じよ」
「じゃあ、滝川先生が持ち歩きますか?」
「それも困るわね。今日、私は飲みに行くから、失くしてしまったら大変だわ」
「ファイルの中に入れておきますか?」
「唐島のファイルではなくて、他のファイルの中に入れておいたら分からないんじゃないかしら。あの証券会社の事件の箱ファイルの中に入れて置くわ。あの事件は書証が多いから、紛れて分からなくなるわ」
「自分で分からなくならないように、気をつけてくださいね」
伊藤がいたずらっぽい眼をして言った。
川上が、例の、使われていない、外人弁護士用の部屋から出てきたのは、午前1時を過ぎてからだった。30分ほど前に、26階の電気は全部消えたが、忘れ物をして戻って来るという可能性もあったので、しばらくは部屋の中で様子を窺っていた。
前回と違って、今度はいろいろと仕事があった。川上はまず、ワープロセクションにあるデータベースが入っているコンピューターを起動し、そこから10メートルほど離れている別のコンピューターも起動した。26階にあるコンピューターの中で、電話回線につなげるものは3台しかなかったので、そのうちの1台のハードディスクにデータベースを入れることから始めなければならなかった。データの容量が大きかったので、フロッピーで移すわけにはいかず、直接ケーブルで繋ぐことにした。川上は昼間秋葉原で買ってきたRS232Cリバースケーブルで2つのコンピューターを繋いだ。コンピューター間のデータの転送は数分で終わったので、今度は通信ソフトを起動し、キングのEメールアドレスにデータを送る作業に入った。これ自体は簡単だったが、データが膨大だったので、送信が完了するまでに2時間ちょっとかかる計算だった。その間、管理事務所の人が見回りに来たらどうしようかと考えたが、名案はなく、見つからないことを祈るだけだった。
川上はデータが送信されている間にもすることがあった。昼間、伊藤の机の上で見たのは、川上が山本六郎のマンションで見せてもらった覚書に間違いなかった。あれを唐島サイドに取られることは、キングにとっては致命的になるはずだったので、キングに相談するまでもなく、川上はそれを取り戻すつもりだった。小さなライトをつけて、伊藤の机の辺りを見たが、それらしきものはなかった。希花の机にライトを向けると、机の上のファイルの中に唐島訴訟のものが数冊あったので喜んだが、あの覚書やそれに関係する書類はファイルのどこにも見当らなかった。希花と伊藤があの覚書を他のファイルの中に隠したとすればその捜索は大変なことになる。部屋の中の小さなキャビネには60冊あまりのファイルがあり、2人の机の引出しにも数十冊あり、更に希花の机の横には20冊ほどのファイルと、ファイルに入り切らない膨大な書類が積み上げられていた。
希花は、大学時代の友人で、上智の文学部の助手をしている男と2時過ぎまで六本木で飲んでいたが、急にあの覚書のことが心配になり、タクシーを拾って事務所に向かった。
26階の中央のエントランスの鍵を開け、中に入り電気をつけた。真っ直ぐ自分の部屋に向かい、箱ファイルの中にあの覚書があることを確認した。何も心配することはなかったのだ、とつぶやいて希花は部屋を出た。気のせいか、東側のドアの閉まる音がした。そちらの方向を見て、希花は様子がおかしいのに気がついた。
通路を挟んで、2台のコンピューターが、青白い光を放っていた。さらに見ると、2台のコンピューターはケーブルで繋がれていた。誰かがまだ残っていて仕事をしているのだろうか。
希花は気味が悪かったので、管理人室に電話をして警備員に来てもらった。26階の全部の部屋を見て回ったが、特に異変はなかった。もう一度コンピューターのところに戻ってきてみると、1台の方のモニターの画面に、通信が完了した旨の表示があった。
「このコンピューターから送信していたんです」
26階の中央にあるランチテーブルの横の秘書の机に置かれたデスクトップパソコンの前で、希花は、伊藤と事務長の川口を前に説明していた。
「このコンピューターが、あのワープロ部門のコンピューターとケーブルで繋がっていたんですね」
伊藤は、廊下を挟んで10メートル程離れたところにあるコンピューターを指差しながら言った。
「何を送ったかわかる?」と希花が伊藤に聞いた。
「ログ(通信記録)を見ればすぐ分かりますよ」と言って、伊藤はコンピューターのマウスを動かした。
「バイナリー送信なので、内容は分かりませんが、115メガバイトぐらいの巨大なファイルですね」
「115メガって言うと、あれかしら?」
「多分そうですね」と言って、伊藤はまたマウスを動かした。
「やっぱりそうだ。このマシンのハードディスクに例のデータベースが入っていますよ」
「ワープロ部門のマシンから、ケーブルを使って移したのね」
「セキュリティーを設定しとくべきでしたね」
「この事務所で鍵のかかるのは、事務長のところの小さな金庫だけですもの。データベースのセキュリティーなんか誰も考えないわ」
「でも、何のために、そんなものを盗っていったんですかね?」と苦笑いしながら川口が言った。
「あれを分析すれば、うちの仕事の内容が全部分かってしまうでしょ」と希花が言った。「でも、動いている案件は入っていないのですから、致命的なことにはならないと思いますけど」と伊藤が言った。
「古いものでも、M&Aの買収価格なんかが分かったら困るわね。でも、そのためにわざわざこんなことをするとは思えないけれど……」
「この書証を持っているのはいやよね。昨夜は、これが心配で戻ってきたのよ」
部屋に戻った希花は、書証を箱ファイルから出しながら言った。
「君原先生に全部渡しちゃえばいいんですよ。今日の午後、バンコクから戻って来られるんですよね」と伊藤が言った。
「私は、内部に誰かいるんじゃないかと思うの。昨夜だって、外部から誰か侵入したと考えるのはおかしいわ」
「関係あるかどうか、分からないんですが……ちょっと変わったことがあったんですよ。もう2週間くらい前になりますが、FMラジオを聴いていたら、急に田中先生の声が聞こえてきたんです」
「何、それ?」
「盗聴だと思うんです。たまたま、周波数が合って受信できたんだと思うのです」
「それ、大変なことよ。何で、もっと早く言ってくれなかったの?」
「いやぁ……事務所の中がごたごたしていたから、パートナーの先生の誰かがやったのかと思ったんです」
「で、その盗聴器はどこに仕掛けられていたの?」
「いや、田中先生の部屋の中を勝手に調べるわけにはいきませんし、田中先生に盗聴されていますよって教えるのも、ちょっと……。こういうのって、落とし物の財布を持ち主に届けるのと違って、被害者からもいい感じを持たれないんですよね。お前も聴いていたんだろうって思うんですよ」
「気が弱いんだなぁ……普通、どういう所に仕掛けるの?」
「電気が必要ですから……コンセントとか……蛍光燈とか……」
「電池でもいいの?」
「もちろんです」
「じゃあ。電卓は?」と、希花は机の上にあったマーシャル&野村のマークが入った電卓を取り上げた。
「ちょっと貸して下さい」
伊藤は電卓に顔を近づけた。
「ここに穴が空いてますね」と伊藤は電卓の右側面にある小さな穴を指差した。
「ここに、マイクがあるのかもしれません」
伊藤は、自分の机の引き出しから小さなドライバーを取り出し、電卓の裏側のプレートを取り外した。
「やっぱりね。ここにマイクがありますよ」と伊藤は基板に貼り付いている、ピンのような物をドライバーの先で示した。
0時40分頃、川上は西城と連れ立って食事に行った。希花は、正午前から、通路に面して並べられた秘書の机でコンピューターを操作するふりをしながら、川上が席を離れるのを待っていた。
希花は川上が出ていくのを確認すると、紙袋を持って川上のブースに向かった。川上の机の上には、ミネラルウォーターのペットボトルと水が半分入ったガラスのコップがあった。コップは事務所の食器棚にいくつも並んでいるものだった。
希花は、右手に軍手をはめてから、紙袋に用意した同じ形のガラスのコップを取り出し、川上の机の上にあるコップとすりかえた。
部屋に戻った希花は、机の上の名刺ケースのKのインデックスのところから、清田の名刺を取り出し、電話した。清田は急な呼出しに困っていた様子だったが、結局押し切られ、8時に西麻布のフレンチレストランで会うことになった。
そのレストランは、西麻布の静かな住宅街にある瀟洒な洋館の中にあった。
清田は遅れていたので、希花は1人でメニューを眺めていた。コース料理のみだが、前菜、温前菜、スープ、魚料理、肉料理が何種類かある中から、1品ずつ選べるようになっていた。前菜では、キャビアを取りたかったが、追加料金が必要だった。今日は、誰が払うんだろうか、と希花は考えた。
8時を10分程過ぎて、清田がやって来た。走って来たらしく、暑い、暑い、と言いながら上着を脱いだ。
「今、マスコミで騒がれている奴でてんやわんやで……なかなか抜け出られなくて……」
「ごめんね。いつもわがまま言って……」
「いいんだよ。滝川さんから電話をもらえるなんて、滅多にあることじゃないんだから」
清田は、学生時代にラグビーをしていたとのことで、ガッシリとした体格をしていて、毛深かった。面食いの希花としては、とても連れて歩きたい男の中には入らなかったが、最近の希花は、男は容姿のみではない、と考えるようになっていた。
清田は、プロポーズを断られてからも頻繁に手紙をよこしたが、希花は1度も返事を書いたことがない。修習生時代には、希花の好みで、フレンチやイタリアンにつき合わせたが、この店にはその当時1回来たことがあった。そういえばこのレストランに来た時だった、と希花は思い出した。帰り道の暗がりで、清田がキスをしたいと言った時に、希花がけんもほろろに撥ねつけたのだった。あの時は随分酷いことを言ってしまった。
希花と清田は、実務修習地が京都で、1年4ヶ月行動を共にした。修習が終わって5年以上経っているので、先ずその当時の仲間の消息について互いに情報を交換した。 温前菜のフォアグラのソテー大根添えと手長エビのグリルしそ風味が運ばれてくる頃には、話題は黒田のことになっていた。
「うちの事務所じゃあ、黒田先生については、内部告発があったに違いないってもっぱらの噂なの」
「それは聞いてないけど……」
「でも、株の取引から逮捕まであまりにも短かったでしょ。普通は、捜査にもっと時間をかけるものじゃないの?」
「確かに我々もびっくりしたんだ。でも、証拠はそろっているというし……」
「どんな証拠?」
「これは噂なんだけど……絶対に人に言っちゃあだめだよ」
「絶対に言わないわ」
「黒田さんのファイルが手に入ったというのだ」
「どこから手に入ったの?」
「不思議な話なんだけど……アメリカからだって言うんだ」
「アメリカの法律事務所?」
「それは知らないけど、アメリカから捜査の要請があったと言うんだ」
「アメリカの何処から?」
「これまた信じられない話なんだけど、この前ワシントンで日米首脳会談があったでしょう。あの時に、アメリカの大統領が日本の首相に捜査を要請したと言うんだ」
「うそでしょう。なんで、黒田先生の逮捕を、アメリカの大統領が要請するっていうの?」
「大統領が直接言ったんじゃあないのかもしれないけど……それにしても、ぼくは、あり得ないと思うけど、部内には情報通と称する奴がいて、そいつがそうだと言っているんだよ」
希花は、やっと、全体の構図が見えてきたような気がした。川上が来て、あの電卓を配った。寺本先生のところへSH&Gから買収の申し出があった。黒田先生がそれに反対した。そして、黒田先生が逮捕された。それに、この前のデータベースの件。
でも、T&Kを買収するために、こんな大掛かりなことをするかしら。アメリカの大事務所だったら、大統領を動かすことぐらいできるかもしれないけれど、黒田先生を逮捕するために、そんなことまでするのかしら。大体、T&Kを買収して、どんな良いことがあるのかしら。日本には、もっと良い事務所が幾つもあるのに。
「うちの事務所には、スパイが送り込まれているらしいの」
「スパイ?」
「日系三世という触れ込みなんだけど、私は絶対違うと思う。」
「……」
「彼女の日本語は上手すぎるし、英語がちょっと変なのよ。彼女の英語はうまいけれど、子供の頃からアメリカで育った人とはアクセントが違うの」
「それだけで、スパイだという訳ではないでしょう」
「いろいろと他にもおかしいところがあるんだけど、まず、日系三世じゃあないってことを証明したいの」
「どうやって?」
「これを調べてもらいたいの」
希花は、ハンドバッグの中から茶色の紙袋を取出した。
「この中には、彼女が使っていたガラスのコップが入っているの。ここから指紋が検出できるでしょ。彼女が、日本人で、スパイのようなことをやる人なら、きっと日本での犯罪歴があると思うの」
「しかし、それは、警視庁の管轄だからなあ……」
「警視庁にもお友達はいるでしょう?」
「警視庁鑑識課か……いないことはないけれど」
「もうこんなことは頼まないからぁ。ねえ、お願い」
これを断ったら、希花から電話がかかってくることはなくなるだろう、と清田は思った。勿論、検事が、私的な目的で、指紋の照合をすることなどできるわけはなかったが、希花に頼まれると、ノーと言うわけにはいかなかった。とにかく預かってみて、努力したけどだめだった、ということでも仕方がないんじゃないか。清田は紙袋を受け取った。
川上からデータベースを受領するとすぐに、キングはSH&Gの弁護士で日本語に堪能な者に集合をかけた。データベースの転送を受けたSH&Gの東京事務所も同時にデータベースの検討に取りかかった。
データベースのうち君原に関するものは15メガバイトを少し超えたが、この文書を印刷するとA4判の用紙を積み重ねて70センチ以上の高さになった。SH&Gのニューヨーク事務所に集められた15人と東京事務所の8人はこれらの文書を手分けして読むことになったが、相互の発見を迅速に伝え合うことを可能にするために、両事務所のテレビ会議システムは常時相手方の検討風景を映し出していた。
文書の検討を始める前に、キングは次のような点に注意して読むようにと言った。即ち、文書の内容が違法である可能性があるものについてはマークすべきである。違法な内容についても、2つの種類があり、一つは自分のクライアントの相手方に対して違法行為を行う場合、例えば相手方を脅迫するような場合がこれに当たる。もう一つは、クライアントに対して違法行為をするように教唆する場合、例えば詐欺をするようにそそのかす場合がこれに当たる。次の類型として注意すべきものは、文書の内容が不当な場合である。例えば、誤った法律解釈に基づいてクライアントにアドバイスをしている場合がこれに当たる。最後に注意すべき類型としては利益相反がある。例えば、自分のクライアントと紛争関係にある相手方に助言をした場合などはこれに当たる。
ニューヨーク時間の午後8時に開始された検討は、意外にもその日のうちに終了した。ニューヨークの時計が午前零時を指そうとした時、ニューヨーク事務所の弁護士のひとりが「eureka(発見した)!」と叫んで立ち上がり、テレビ会議のカメラの前にVの字にした指を突き出した。ちなみに
eureka
はアルキメデスが比重の原理を発見した時に発したといわれる言葉である。
君原は、キング弁護士からの電話が入っていると秘書に伝えられた時に、来るべきものが来たと覚悟した。
希花から、データベースが何処へか送信されたことを聞いた時、君原は、そのターゲットが自分だと直感した。あのデータベースの中には、君原が外部の者に見られたくないものが入っていた。データベースが完成するまでに、削除しようと思っていたファイルがひとつだけ残っていたのだ。
君原が電話に出ると、キングは陽気に話し始めた。君原については、いろいろと良い評判を聞いていること。君原の英語力は、日本の弁護士としては傑出していること。そのような君原が、事務所を辞めると聞いたが、考え直す気がないのか、等々。
君原は、SH&Gによる買収に反感を持って辞めるのではなく、自分なりの新しい活動を計画していると説明した。
キングはやっと本題に入った。
「ユナイテッドモータースは君のクライアントだったね」
「そうだが……それが何か?」
「ユナイテッドモータースがオートローンの契約のことで、神田信販から訴えられたことがあったね」
「あれは、和解で片付きましたよ」
「神田信販というのも、君のクライアントらしいね」
「時々、小さな仕事を頼まれる関係だけですけどね」
「1994年3月2日に神田信販に手紙を出しているね」
「何が言いたいんです?」
「あの手紙は、和解の条件についてユナイテッドモータースがどの程度のことを考えているか、と聞かれて、それに答えているものだね」
「和解で解決するのは、両者のためになることだと思ったからですよ」
「手紙の最後に、読んだらすぐシュレッドしてくれ、と書いてあるね」
「……」
「君は、ユナイテッドモータースの訴訟代理人であったのに、依頼者に断りなく、相手方に助言をしているね。これは利益相反行為だね」
「……」
「これは、弁護士法違反だし、懲戒事由にもなるね」
「……‥」
「ユナイテッドモータースがこれを知ったら、どうすると思う?
勿論、君に仕事を頼むのはやめるだろう。それだけじゃなくて、損害賠償請求をしてくるかもしれないよ」
「分かった。どうすればいいんだ」
「君に、T&Kを辞めないでほしいんだ。それから、唐島監督の例の訴訟だけど、あれを、我々が指定する弁護士に引き継がせてもらいたいのだ」
「唐島監督の訴訟?まさか、あれが目的だったのか?」
「まあ、それはともかく、条件はこの2つだけだ。そうすれば、我々は何もしないし、むしろ、君のためになることをいろいろと考えたいと思う」
「私がT&Kを辞めても、唐島監督の訴訟をそちらの指定する人に引き継ぐということではだめなのか?」
「それはだめだ。唐島監督は、T&Kではなく君に依頼している訳だから、君が事務所を辞めたからって何も変わらないと思っている。それを、訴訟を残して事務所を辞めて、事務所が更にそれを他の人間に任せるなんていうのは、おかしいだろう。唐島監督が、不審に思うようなことは絶対にできない。君はT&Kに残り、君から直接、唐島監督に言ってほしいのだ。T&Kは訴訟の相手方の法律事務所に買収されてしまったので自分は唐島監督の代理人は続けられない、でも信頼できるいい弁護士を紹介する、と」
「何を要求されているかはよく分かった。とにかく急な話だから、少し時間をもらえないか」
「30分。30分したら、また電話するから、その時にイエスかノーで答えてくれ」
「分かった」
君原は、秘書に本屋に行くと言い残して、事務所を出た。
虎ノ門から新橋方向に歩きながら、君原は考えていた。結論は、電話を切る前にもう出ていた。あの男に逆らうことはできない。逆らえば身の破滅だ。ユナイテッドモータースの仕事は君原の全収入の4割近くを占めるから、それを失うわけにはいかない。懲戒とか損害賠償請求についてはあまり心配していなかったが、これが明らかになれば、ユナイテッドモータースが仕事を引き上げることは確実だった。アメリカの大企業は、こういうことについては非常に厳しい。
神田信販へのアドバイスを書面でしたのは君原らしくないミスだった。ユナイテッドモータースの和解案が3通りあり、それぞれ和解金の算出方法が違っていたのでそれを正確に伝えようとしたのがあだになった。しかし今悔やんでも仕方がない。
新事務所については、アソシエイト、パラリーガルを含め、君原についていくことを表明した者が数人おり、彼らに説明しなければいけない。君原が中心となって組織作りを始めていた法律事務所のネットワークも、T&Kに残るのであれば意味がなくなる。主唱者としてはみっともないことだが、抜けさせてもらおう、と君原は思った。
30年前の、全共闘を抜けた時のことを思い出していた。自分は、何一つ変わっていない。大きな力の前には足が竦んでしまう。思想も、信念もない人間なのかもしれない。あの時、軽蔑する、という言葉を残して去っていった女がいた。希花は何と言うだろう。
君原がT&Kに残ることが決定してから2日後に、SH&Gから50頁余りの買収契約書の草稿がクーリエで届いた。契約書の署名欄には、T&Kに残ることになった君原を含む15人のパートナーの名前が列記されていた。それから2日後、キングに率いられたSH&Gの代表団が来日し、契約書の最終の詰めに入り、その日のうちにサイン用の契約書が作成された。調印は、7月7日金曜日の午後6時から、T&Kの第1会議室で行われることになった。会議室の大きなテーブルの上には、日米両国の国旗を交差させた置物が、ブラインドの間から差し込む夏の日を受けて長い影を造っていた。
希花は、午後から大阪に出張することになっていたので、その準備をしていた。唐島訴訟の例の準備書面と書証は、君原が問題はないと言いながらなかなか返してくれず、希花は、月曜日の朝の法廷に直接持っていこうと思っていた。
希花が事務所を出ようとした時に、清田から電話が入った。
「あの件だけど、面白いことが分かったよ」
「え、調べてくれたの?」
「普通は、こういうことはできないんだけど、無理を言ってやってもらった」
「それで、どうだったの?」
「前科はない」
「なんだぁ、そうかぁ……」
「彼女には、前科・前歴はなかった。でも、指紋の記録はあったんだよ」
「何で?」
「91年まで、在日外国人が外国人登録をする時には、登録原票と登録証に指紋を押さなければいけなかったんだよ。そのデータが警視庁には残っているんだ」
「在日韓国人?」
「そう。在日韓国人三世。李華美。29歳」
「そうかぁ。そういうことだったのか」
希花は喫茶店で韓国語で電話をしていたクリスティーヌ川上を思い出した。でも、在日韓国人三世が何故アメリカから来たのだろう。
7月10日月曜日、希花は訴訟の準備があったので9時10分に事務所に着いた。いつもであれば、まだ閑散としている事務所が、その日は何故かざわついていた。自分の部屋に着くまでに、巻尺を持ってパーティションの高さを測っている内装関係の人間らしい2、三名と、外国の弁護士らしき男2名とすれ違った。
部屋に入ると、伊藤がコーヒーを飲んでいた。
「早いのね」
「落ち着かないので、いつもより早く来てしまいました」
「訴訟のこと?」
「あっ、先生は金曜日の午後いなかったんですよね」
「何があったの?」
「買収されちゃったんですよ」
「えっ!」
「金曜日の夜、第1会議室で買収契約の調印があって、我々は、SH&Gの東京事務所になったんです。今日の昼、我々は第1会議室に集められて、キングというヘッドパートナーのお話を聞かなければいけないようですよ」
「すごく急な話なのね。君原先生はどうしたの?」
「金曜日の夜遅く、君原先生の部屋に呼ばれてお話をうかがったんですが、君原先生は事務所に残ることに決めたそうです」
「ほんと?もう辞表は出したって聞いていたけど」
「それが、どうしても辞められなくなったようなんです」
「唐島監督の訴訟はどうなるの?SH&Gはハーキュリーズピクチャーズの代理人なのだから、私たちがこのまま唐島監督を代理することはできないわ。君原先生が外の弁護士を紹介するのかしら?」
「そこらへんははっきり言われなかったんですけど、どうも、SH&Gの息のかかった弁護士がやることになりそうですよ」
「それじゃあ、唐島監督の権利の擁護なんかできるわけないじゃないの。全然納得いかないわ」
「これは、君原先生の秘書から聞いたことなので、秘密にしておいてほしいんですけど……君原先生は、キングに脅されたらしいんですよ。例のデータベースをネタに」
「連中が盗っていったって言うの?それで、君原先生を辞めさせないようにしたの?でも何故?」
「君原先生が唐島監督の訴訟を持って出るのを阻止したかったらしいんですよ」
ジグソーパズルの最後の欠片が穴を埋めて、それまで意味を成さなかった形が、突然、一つの大きな絵になったような気がした。黒田の逮捕も、買収の話も、データベースを盗み出したのも、全部あの訴訟に勝ちたかったからだったのだ。それなら、あの山本六郎のところに川上らしき女が来て覚書を手に入れようとしたのも理解できる。あの訴訟が、彼らにとって何故それほどの意味があるのかは分からなかったが、スパイを送り込み、大統領をも動かすほどの、大事なものに違いなかった。
「君原先生が、事務所を辞めるか辞めないかというのは、君原先生の勝手ですけど、そのために、唐島監督の権利が守られなくなるとすれば、それはおかしいと思います。唐島監督には、誰の影響も受けないで、唐島監督の立場に立って判断できる弁護士が就くべきです。そして、その弁護士に対して、我々は全ての資料を引き渡して、今現在我々が持っている全ての情報を話すべきです。それをしなければ、我々は弁護士としての最低の職務を果たしていると言えません」
君原は9時前から事務所に来ていて、忙しく動き回っていたが、法廷に行こうとカバンを取りに部屋に戻ったところを希花につかまった。
「それはよく分かるんだが……我々は、買収契約書にサインした時から、SH&Gの支配下にあるのだよ。だから、彼らの指示なしに勝手なことはできない……」
「SH&Gの支配下にあるために、依頼者の権利が守れないというのなら、事務所を辞めればいいのだわ。先生は、彼らに何か弱みを握られているのかもしれないけれども、弁護士である以上、依頼者のために、自分が傷つかなければいけないこともあるでしょう。それができなければ、弁護士は辞めたほうがいいわ」
「……」
君原は、顔を上げることができずに、机の上に広げた契約書を意味もなくめくっていた。
「滝川先生。随分恐い顔をしていますよ」と伊藤が言った。
「君原先生を見損なったわ。あんな男だとは思わなかった。今日の法廷は自分1人で行くって言っていたわ。きっと、あの覚書は握り潰すつもりだわ」
「……」
「伊藤先生、何か方法はないかしら。あの覚書を出さなければ、唐島監督は負けてしまうわ。君原先生に覚書を渡すんじゃなかった」
「一つ方法がありますよ」
「何それ?」
「書証を作る時に、甲号証のスタンプが上手く押せなかったコピーが1枚あるんですよ。それがまだとってありますから、それを原本として書証を作ればいいんですよ」
「そうかぁ。写しを原本として提出するっていうことね」
「それを提出することで、被告の提出した書証の証明力が大きく減殺される筈です」
契約書はハンコを押したオリジナルのみが証拠となるわけではない。特に今回のような場合、被告の提出した書証の欠けている部分に何があったかを被告は証明し得ていないのだから、その部分を明らかにするコピーは大きな証拠価値を持つ。
希花が611号法廷に駆け込んだ時、丁度3人の裁判官が退廷するところだった。
原告被告の代理人もそれぞれ書類をカバンにしまい、帰り仕度をしていた。
「裁判長!」と希花が傍聴席の後方から叫んだ。
「原告……原告代理人の……滝川です」タクシーを降りてから全力で走って来たので、息が切れて言葉がうまく出てこない。
「甲第……甲第八号証を提出します」
3人の裁判官が振り返った。
「滝川さん、あなたはもう解任されているんだよ」と君原は原告代理人席の隣に座っている弁護士を示して言った。「唐島監督が判を押した解任届けは今日裁判所に提出しました。勿論、私も伊藤先生も同時に解任されて、今はこちらの島原先生が原告代理人なんですよ」
希花は茫然と立ちつくしていた。
君原は今度は3人の裁判官の方を向き、「打合せが不十分で失礼いたしました」と言って一礼した。
希花は、裁判所からオフィスへの道を1人で歩いていた。もう一度説明させてくれ、という君原を振り切って、希花は法廷を出た。話を聞く必要はなかった。希花は言い訳をする男が嫌いだった。
朝方降った通り雨が舗石を濡らしていたが、夏の強い太陽がその跡を消しつつあった。街路樹の下を歩く希花の白い横顔に、木漏れ日が降りかかっていた。
虎ノ門の交差点を渡り、商船三井ビルの前あたりに来たところで、希花は、反対方向から歩いてくる川上と目が合った。川上は重そうなボストンバッグを持っていた。今朝見たウィークリーレポートには、川上が急に帰国することになったと書いてあった。
軽く会釈して通り過ぎようとした川上に、希花が呼びかけた。
「李華美」
クリスティーヌ川上こと李華美は振り返った。
「そう。在日韓国人三世、李華美。生年月日1971年1月18日。同い年ね」
「そうだったら?」
華美は動じることなく、希花の目を見ていた。
「聞きたいことがあるの」
「……」
「あなたは黒田先生のファイルを盗みだした。そして、データベースのファイルをアメリカに送信した。そのおかげで、黒田先生は逮捕され、君原先生は裏切った。そしてT&Kは買収された」
「……」
「あなたがやったんでしょ……全部あの映画のためだったの?」
「知らないわ……知っていても言えないわ」
「あなたは日本を憎んでいるの?日本で育った人なんでしょう?どうして、日本を売り渡すようなことをするの?私たちがあなた達に悪いことをしたから?」
「それには答えられるわ」
華美は一言一言噛み締めるように言った。
「私は民族とは関係がない。民族も国家も私を守ってはくれない。私を守るのは私だけ」
「私達は自分を守らなかったということなのね」
「隙があれば狙われるわ」
「隙だらけだったのね」
華美は黙っていた。答えは自明だった。
「もう帰るんでしょ。仕事が終わったから」
「そう」
「またどこかで会うかもしれないわね」
「世界のどこかでね」
「その時は負けないわ」
「楽しみにしているわ」
心地よい風が2人の間を通り過ぎた。
あの喫茶店で初めて川上を見た時から抱き続けていた敵意が消えていることに希花は気付いた。ひとつの戦いが終り、2人の戦士は相手に自分と相似の資質を認めていた。
「じゃあ元気で。アンニョン(さよなら)」
韓国語で希花が言った。
「アンニョン ト マンナヨ(さよなら。また会いましょう)」
華美は、一瞬微笑み、目礼して去って行った。
1週間後滝川希花はバリ島にいた。
何をおいても希花はひとりになりたかった。ここ3ヶ月程の間に起きたいくつかの事件については一応の説明は付けられたが、それが自分にとってどのような意味を持つかを考えると頭が混乱した。目をつぶっていれば元の平和で退屈な日々が戻ってくるような気もしたが、心の中にはそれは許されないと囁く声もあった。
バリ島は3度目だった。最初はヌサ・ドゥアのきれいなホテルに泊まり、2度目はクタのシャワーもないロスメン(民宿)に1ヶ月間滞在した。クタはビーチを10歩も行けば物売りに捕まる活気にあふれた場所で、その雰囲気が嫌いではなかったが、今希花に必要なのは静寂だった。
希花が選んだのはヌサ・ドゥアのプトゥリ・バリという中級のホテルだった。日本人の利用者が比較的少なく、ぼんやりと考え事をするには良いのではないかと希花は思った。しかし、女性の一人旅だということが分かると、ヨーロッパから来ている男達がうるさくつきまとって来た。
結局昼間は落ち着いて考え事をする環境にはなく、夜ベッドの中で考えていると目が冴えるだけで何の結論も出てこなかった。午前3時になっても寝付かれないので希花はホテルの庭を歩いてみようと思った。
この時間は流石に外には人影はなく、昼間イタリア人の男達がバレーボールをして騒がしかったプールも静まりかえっていた。プールの脇を抜けると黒い海が広がっていた。波は静かで海も半分眠りについているかのようであった。
波打ち際まで行って希花は波の引いた後の濡れた砂が光っているのに気付いた。波が宝石を運んで来たかのように青白く光るものが幾つも砂の中に残されていた。視線を移すと、波の引いた後の砂浜は遠くまで星空のようにキラキラと光っていた。夜光虫だった。
希花は寄せてくる波に足が洗われる位置に腰を下ろした。ゆっくりと砂の上に仰向けに寝てみると、満天の星が覆い被さってきた。それは作り物のような星空だった。夥しい恒星がその存在を主張し、その背後には銀河が光の粉を撒き散らしたように横たわっていた。星空と夜光虫の光の間にはさまれて、希花は体が重さを失って夜空に浮上していくように感じた。流れ星が銀河をよぎり消えた。
その時希花は自分の内部にある宇宙が外部の宇宙に呼応して震え、ひとつの秩序が生まれるのを感じた。無造作にばら撒かれたような星々がそれ以外にはない必然の位置にあることが確認され、宇宙は明白な意味を持った。
弁護士を辞めよう、と希花は思った。法律は人間がつくった壮大な建物だが、天に届くものではない。いや、本当に天に向かって伸びていっているのかさえ定かではない。それを見極めるには法律という建物の外に立って眺めなくてはいけない。それが私に出来るかどうか分からないけれど、私も宇宙の一部なのだし、私の中にも宇宙がある筈だから、それを試みる資格はあるに違いない。
そう考えると方程式の解答はおのずと明らかになった。まず、今の事務所は辞めよう。あそこにいても美しいものが見えてくるとは思えない。その後どうするかは気楽に考えよう。何をやっても勉強にはなるだろうし、また一生の選択をここでする訳でもない。やり残したことがあるとすれば唐島監督の訴訟だろう。あれをあのままにしておくことは出来ない。事務所を辞めれば私を拘束する者はいないのだから、唐島監督に助言することはできる。田代さんとは友達のようになっているから、彼女を通じて言えばいい。君原先生が裏切ったということまで伝える必要はないけれど、少なくとも有利な和解が出来るところまでは持って行きたい。
天頂近くにひときわ輝く4つの星があった。あれが南十字星だろうか。4つの輝く星は希花の小さな決意を見守ってくれているようだった。
* * *
唐島監督の訴訟は、程なく和解で決着した。和解の条件は明らかにされていないが、ハーキュリーズピクチャーズは、唐島監督に相当な金額の和解金を支払ったとのことである。
寺本がSH&Gのパートナーになる話はたな晒しにされ、1年後、雇用契約の満了により寺本はSH&G東京事務所を去った。もっとも、寺本はその前から弁護士業務に興味を失っていた。現在は、真鶴半島の海が見える丘の上にある別荘に引きこもり、100坪の菜園で過ごす時間を何よりも大切にしている。海を見ていると、時々、クリスティーヌ川上のことを思い出し、耐え難い程の寂しさを感じることがあるが、全てが夢の中の出来事だったようにも思える。
黒田は、執行猶予付きの懲役判決を受け、弁護士に復帰する道はなくなり、黒田自転車店を継ぐことになった。黒田は、黒田自転車店をチェーン店化し、いずれ、日本一の規模にすることを夢見ている。
李華美は、スパイ稼業を一時中断し、ロサンゼルスのロースクールに入った。3年後には、カリフォルニアで弁護士資格を取るつもりだ。
君原は、SH&Gのパートナーになり、日米間を忙しく往復するようになった。いつの頃からか、君原の名刺の英文で表示された裏面には、Tetsuya Kimiharaではなく Ted Kimiharaと書かれるようになっていた。
希花は、買収後間もなく事務所を辞め、知り合いの弁護士の事務所で、それまで経験のなかった刑事弁護の仕事を手伝っていたが、やがてその事務所からもいなくなった。翌2001年の弁護士名簿からは、滝川希花の名前は消え、その行方は杳として知れない。